リスキリングとは?意味・目的から効果的な推進方法まで徹底解説
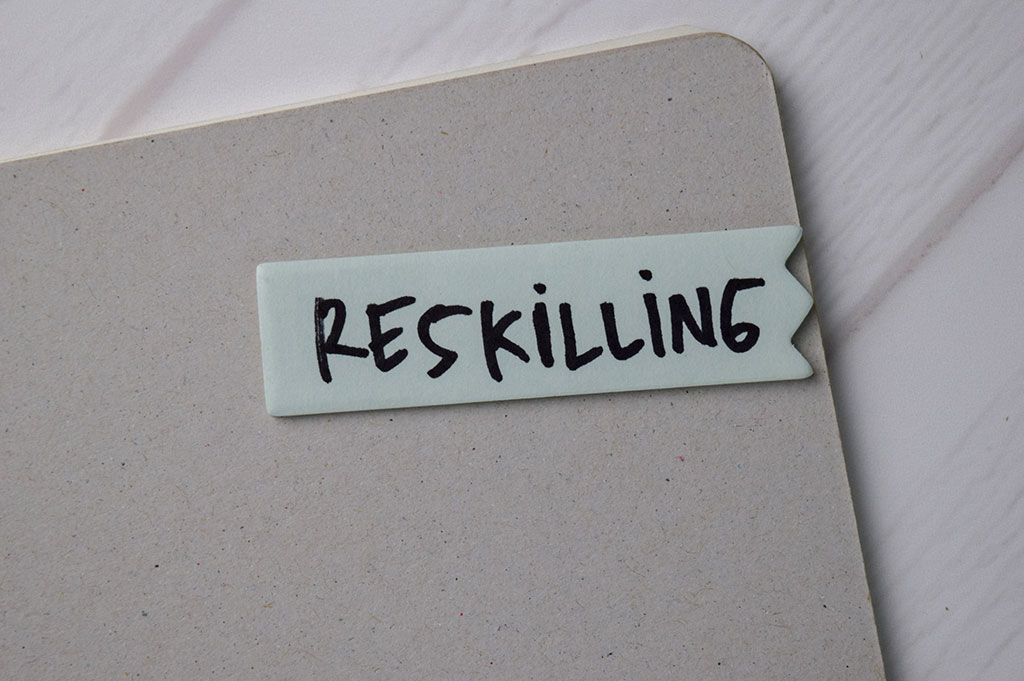
⇒【マンガでわかる】「360度評価」のメリットやデメリット、失敗しないための導入方法が詳しく学べる資料を1分でダウンロード
「採用を増やしても人が足りない…」
「研修プログラムはあるけど、効果がいまいち…」
日本企業が抱える人材課題は、年々深刻さを増しています。
経済産業省の調査によると、2030年頃までに45万人程度のIT人材が不足するとされています。
ただし、この数字は決して悲観するべきものではありません。むしろ、社員一人ひとりの可能性を広げるチャンス。環境は着実に整いつつあります。
政府も本腰を入れており、多額の支援を行うことを決めています。企業にとって、リスキリングに取り組む絶好のタイミングが訪れています。
もちろん、リスキリングは簡単な取り組みではありません。しかし、計画的に進めることで、採用コストの削減だけでなく、会社全体の成長にもつながる可能性を秘めています。
この記事では、リスキリングの意味から実践的な進め方まで、具体例を交えながら解説していきます。
目次
リスキリングとは
リスキリングは、今持っているスキルを活かしながら、新しい分野で必要な知識や技術を身につけることです。
最近のビジネス用語のように聞こえるかもしれませんが、その本質は、企業と社員の可能性を大きく広げる取り組みにあります。
以下では、リスキリングの具体的な特徴について詳しく解説します。
【リスキリングとは】
・既存の知識を活かして新しい分野にチャレンジできる
・デジタル時代に必要な人材になれる
・会社と自分の成長につながる
既存の知識を活かして新しい分野にチャレンジできる
営業やマーケティングの世界では、顧客心理の理解が重要です。
この深い洞察力は、デジタルマーケティングの分野でも大きな強みとなります。データ分析の結果を読み解く際、長年の経験が独自の視点をもたらすことも。
デジタルスキルと従来の専門性を組み合わせることで、新たな価値が生まれています。
プログラミングやデータ分析のツールは、使いこなすための入り口が整備され、以前より習得しやすくなっているのです。
デジタル時代に必要な人材になれる
「エクセルしか使えないから…」
「今の仕事がなくなるかも…」
三菱総合研究所の調査では、今後10年で事務職や生産職が減少すると予測しています。しかし、この変化は新たな機会の到来でもあります。
例えば、経理業務。RPAによる自動化で単純作業が減り、より深い財務分析や経営判断のサポートにシフト。業務の質が大きく変わることで、やりがいも増していきます。
データ分析やAIの基礎知識があれば、どの部門でも活躍の場は広がります。専門スキルと組み合わせることで、より価値の高い提案や判断ができるようになるためです。
会社と自分の成長につながる
単純作業から解放され、より深い思考が必要な仕事にシフトする。それがリスキリングの一つの形です。
例えば経理部門では、RPAの導入で請求書処理の自動化が進み、より本質的な経営分析に時間を使えるように。
営業部門でも、データを活用した提案ができるようになり、顧客との対話が深まっていきます。
何より大きいのは社員の意識の変化かもしれません。「こんなことできるんだ」という発見が、次の挑戦を生み出しています。
リスキリングの重要性と必要性
デジタル技術の進展は、企業に大きな変革をもたらしています。
一方で、そのスピードについていけない組織も増えています。
なぜ今、リスキリングが重要なのか、以下では、の具体的な理由について詳しく解説します。
【リスキリングの重要性と必要性】
・デジタル化で求められる能力が変化している
・人材不足を社内育成で解決できる
・国からの手厚い支援を受けられる
デジタル化で求められる能力が変化している
IPAの「DX白書2023」の結果は、衝撃的でした。8割を超える企業がIT人材の不足を感じています。しかし、単なる技術者不足という問題ではありません。
業務とデジタルの両方を理解する人材。それが、これからの主役です。
製造現場の知識を持つエンジニアが、生産ラインのデジタル化を成功させるケースもあります。
現場を知る人だからこそ、効果的なデジタル活用が実現できるのです。
自動化に対応できる
RPAやAIによる業務自動化が進む中、業務フローを理解した上でデジタルツールを使いこなすスキルが重要になっています。
例えば、経理部門では、定型的な仕訳作業の自動化により、より高度な財務分析に時間を使えるようになりました。
工場の製造ラインでも、センサーデータの活用による品質管理が一般的になっています。ベテラン作業員の経験則をデジタルデータと組み合わせることで、より精度の高い品質管理が実現しています。
新技術を理解できる
技術の進歩は加速度的です。クラウドサービスやビジネスツールは日々アップデートされ、新しい機能が追加されています。
こうした変化に柔軟に対応し、業務に活かせる力が必要です。
人材不足を社内育成で解決できる
デジタル人材の採用市場は年々厳しさを増しています。
給与水準は上昇を続け、即戦力人材の確保は困難になっています。
しかし、社内育成には大きなメリットがあります。業務への理解がある社員は、新しいスキルの実践的な活用が早く、現場の課題解決に直結する形でデジタル技術を活用できるのです。
採用費用が減る
中途採用では、年収の30%程度が紹介手数料として必要になることも。
一方、社内育成では、その費用を研修投資に回すことができます。
政府の支援制度も活用できるため、コスト面でも効率的です。
採用の手間が減る
採用活動には多くの時間と労力が必要です。
書類選考、面接、入社後のフォローなど、一連のプロセスは人事部門の大きな負担となります。
社内育成なら、その時間を人材開発に集中できます。
国からの手厚い支援を受けられる
政府は企業のリスキリングを積極的に後押ししています。
2025年に向けた支援策には、具体的な助成金制度や、教育訓練の環境整備支援が含まれています。
助成金が使える
研修費用の補助から、育成期間中の給与支援まで、様々な助成制度が用意されています。
特に中小企業向けには、より手厚い支援メニューが揃っています。
リスキリングのメリットと効果
企業のデジタル化は、もはや避けて通れない道となっています。
ただし、デジタル化は単なる業務の自動化ではありません。人材の成長と組織の進化、この両輪が重要になります。
リスキリングの効果は、コスト削減にとどまらず、組織全体の競争力向上にまで及びます。具体例を見ながら、その効果を確認していきましょう。
【リスキリングのメリットと効果】
・社員の働く意欲が高まる
・会社全体の成長力が上がる
・人材を活かす経営ができる
社員の働く意欲が高まる
仕事のやりがいは、目の前の課題を解決できるという実感から生まれます。
デジタルスキルを身につけることで、これまで手つかずだった課題に向き合えるようになります。
経理部門の例を見てみましょう。
データ分析ツールを使いこなせるようになった結果、経営に役立つ財務分析ができるようになることも。
毎月の数字を追うだけでなく、将来予測まで踏み込んだ提案ができるため、経営陣との対話も深まっています。
将来の目標が見える
データサイエンティストやAIエンジニアなど、新しい職種が次々と生まれています。
社内でもデジタル活用のリーダーとして活躍できる機会が増えており、キャリアの選択肢は確実に広がっています。
成長を実感できる
日々の業務で新しいツールを使いこなし、課題を解決できるようになる。この小さな成功体験の積み重ねが、自信となります。
特に、若手とベテランが協力してプロジェクトを進める中で、それぞれの強みを活かした新しい価値が生まれています。
会社全体の成長力が上がる
個々の社員がデジタルスキルを身につけることで、組織全体の対応力は飛躍的に向上します。
経営判断のスピードが上がり、市場の変化にも柔軟に対応できるようになります。
製造業では、生産ラインのデータをリアルタイムで分析し、品質管理を強化。サービス業では、顧客データの分析から、新しいサービス開発のヒントを得ています。
まさに、全社を挙げてのデジタル活用が、競争力につながっているのです。
業務の質が向上する
ルーチンワークの自動化により、より創造的な業務に時間を使えるようになります。
部門を超えたデータ共有も進み、全体最適な意思決定が可能に。結果として、顧客満足度の向上にもつながっています。
新規事業が生まれる
データ分析から見えてきた市場ニーズ。それに応える形で、新しいサービスが生まれています。
既存事業のノウハウとデジタル技術を組み合わせることで、独自性の高い事業展開が可能になるのです。
人材を活かす経営ができる
組織の価値は、人材の質で決まります。リスキリングは、単なるスキル習得プログラムではなく、組織の競争力を高める重要な経営戦略です。
例えば、製造業の現場では、熟練工の技能をデジタル化することで、技術の継承が進んでいます。センサーデータと経験則を組み合わせた品質管理システムは、新人教育の効率化にも貢献。結果として、組織全体の技術力向上につながっています。
社員の能力が最大限に発揮される
業務の本質を理解している社員が、デジタルツールを使いこなせるようになれば、その効果は倍増します。
課題の発見から解決策の提案まで、より主体的な行動が生まれます。
例えば、製造ラインでは品質管理のデータをリアルタイムで分析。不良品の発生を未然に防ぐだけでなく、生産効率の向上にもつながっています。現場の知恵とデジタル技術の融合が、新たな価値を生み出しているのです。
会社の評価が上がる
人材育成に積極的な企業として市場から評価され、優秀な人材が集まります。
特に若手人材は自身の成長機会を重視する傾向が強く、充実した育成プログラムは大きな魅力となります。
株式市場でも、人材投資への評価は高まっています。ESG投資の観点からも、人材育成への取り組みは重要な評価指標となっているのです。
リスキリングの具体的な進め方
デジタル時代に必要な人材になるため、多くの企業がリスキリングに取り組んでいます。
しかし、ただ研修を実施するだけでは十分な効果は得られません。
組織と個人の成長につながる効果的な進め方について、具体的に解説していきます。
【リスキリングの具体的な進め方】
・現状のスキル分析から課題が見えてくる
・段階的な教育プログラムが完成する
・定期的な効果測定で成果が明確になる
・人事評価制度との連動が実現する
現状のスキル分析から課題が見えてくる
組織全体のスキルレベルを正確に把握することが重要です。
経済産業省の調査によると、約7割の企業が自社の人材スキルの現状を十分に把握できていないとしています。
部門ごとの特性や、将来必要となるスキルを踏まえて、組織全体のスキル状況を整理していく必要があります。この分析結果が、効果的な育成計画の土台となります。
スキルマップで現状を可視化できる
部門ごとに必要なスキルは異なります。
製造部門では品質管理のデジタル化、営業部門ではデータを活用した顧客分析など。まずは、各部門の現状と目標を明確にすることが重要です。
センサーデータの活用や分析ツールの導入により、これまで経験則に頼っていた判断も、より客観的に行えるようになっています。
ベテラン社員の知見をデジタルデータと組み合わせることで、技術継承も確実に進められます。
必要なスキルとのギャップがわかる
データ分析の基礎知識は、もはやどの部門でも必要不可欠です。
顧客データから商品開発のヒントを得たり、業務プロセスの改善点を見つけたり。デジタルツールを使いこなすことで、業務の質は確実に変わります。
段階的な教育プログラムが完成する
リスキリングを成功させるには、社員それぞれの学び方や理解スピードに寄り添った段階的なプログラム作りが欠かせません。
段階式の学習プログラムを取り入れた会社では、社員のスキル向上に効果が見られるようです。
一気に詰め込むより、少しずつステップアップしていく方法のほうが定着率が高いと言われています。
目標レベルを具体的に設定できる
各段階で「ここまでできるようになろう」という目標をはっきり示すと、社員は自分が今どこにいて、どこに向かっているのかを把握できるようになります。
たとえば「基礎」「応用」「実践」といった具合に区切り、それぞれの段階で身につけるべきスキルや評価基準を明確にして、達成度を「見える化」すると、やる気を保ちやすくなるとされています。
また、目標を達成したら評価や報酬に反映させる仕組みも、モチベーション維持に役立つでしょう。
カリキュラムの内容を組み立てられる
社員個人の学習ニーズと会社が目指すゴールを踏まえて、基本から応用まで体系的に学べる内容を設計することが可能です。
オンラインとリアル研修を組み合わせたり、実際に手を動かすワークショップを取り入れたりと、学び方に変化をつけることで、より効果的な学習環境が構築できるでしょう。
座学だけよりも実践を交えたほうが、記憶に残りやすいという点は多くの教育研究で示されています。
定期的な効果測定で成果が明確になる
リスキリングの効果を適切に把握するには、定量的な指標と定性的な評価の両方が必要です。
効果測定を体系的に実施することで、より効果的なプログラム運営が可能になるでしょう。
測定する際は、「スキルの習得度」や「業務効率の向上率」といった数値だけでなく、本人の自己評価や上司からのフィードバックなども含めると良いでしょう。最近注目されているのは、AIを活用した効果測定ツールです。
学習管理システムにAI分析機能を組み込むことで、個々の学習進捗や理解度を分析し、カスタマイズされたアドバイスを提供することが可能になります。
KPIで進捗状況を把握できる
具体的な数値目標を設定し、定期的に進捗を測定することで、リスキリングの効果を客観的に評価することができます。
「何となく良くなった」ではなく、「〇〇%向上した」と数字で示せることが、経営判断においても重要なポイントとなります。
スキルの習得率や業務効率の向上度、新規プロジェクトの立ち上げ数など、複数の視点から成果を測定することが理想的です。
学習成果をテストで確認できる
定期的なテストや実践的な課題を通して習得したスキルのレベルを確認できます。
単なる知識の暗記ではなく、実際のビジネスシーンを想定した問題設定が効果的です。
「知っている」と「使いこなせる」の間には大きな差があるもの。実践力を測る工夫が必要になります。
個別フォローアップ計画の土台としても。つまずきやすいポイントを特定し、追加学習の機会を提供することで、全体のレベルアップにつながっていくでしょう。
人事評価制度との連動が実現する
リスキリングを持続的な取り組みとするには、人事評価制度との連動が重要なポイントになるでしょう。
リスキリングと人事評価制度を結びつけることで、より効果的なスキル開発が可能になると考えられています。
具体的な方法としては、目標管理制度(MBO)の中にリスキリング目標を組み込み、期初・期中・期末での上司との面談を通じて進捗を確認する方法があります。
また、タレントマネジメントシステムを活用して、組織全体のスキル習得状況を可視化し、評価やキャリアパスの設計に生かすことも一つの選択肢でしょう。
評価基準に反映できる
新しく習得したスキルや、リスキリングへの取り組み姿勢を人事評価に組み込むことで、従業員の学習意欲は大幅に高まります。
評価基準は、スキルの習得レベルだけでなく、実務での活用度や、他の従業員への知識共有なども含めて総合的に設定すべきです。
給与制度に組み込める
リスキリングによって習得したスキルを給与体系に反映させることは、従業員の学習モチベーションを確実に向上させます。
スキルレベルに応じた手当の設定や、昇給・昇格との連動など、具体的なインセンティブを設けることで、継続的な学習を強力に促進できます。
リスキリングの推進体制と支援制度
効果的なリスキリングを実現するには、適切な推進体制を作り、様々な支援制度をうまく使いこなすことが大切です。
ここからは、具体的にどう取り組めばいいのか、詳しく見ていきましょう。
【リスキリングの推進体制と支援制度】
・国の支援を最大限に活用できる
・外部の専門機関と連携できる
・社内の評価制度が整う
国の支援を最大限に活用できる
政府は2025年に向けて、リスキリング支援に5年間で1兆円を投じる計画を発表しています。
人材開発支援助成金の中でも、事業展開等リスキリング支援コースを利用すれば、中小企業なら経費の75%、1人1時間あたり960円の賃金が助成されます。
特に見逃せないのは教育訓練休暇制度の導入支援です。3年間で5日以上の有給教育訓練休暇を設けると、制度導入に関する助成を受けられます。
こうした制度をうまく活用すれば、会社の経済的負担を大きく減らせるのです。
外部の専門機関と連携できる
リスキリングで成果を出している企業の多くは、外部の専門機関とうまく手を組んでいます。
例えば、Microsoft、Google、AWSといった大手IT企業が提供する認定プログラムや、専門教育機関のカリキュラムを取り入れることで、最新技術をしっかり学べる機会を社員に提供できます。
また、地元の商工会議所や公立大学と協力して、その地域ならではの人材育成プログラムを作ることも可能です。
社内の評価制度が整う
リスキリングを長く続けていくには、人事評価制度とのつながりが欠かせません。
評価制度をしっかり整えると、社員の学ぶ意欲が高まり、会社全体のスキルアップにつながります。
さらに、新しく身につけたスキルを給与に反映させれば、学び続けるモチベーションを保つことができるでしょう。
リスキリングを成功させるためのポイント
リスキリングをうまく進めるには、押さえておくべきポイントがいくつかあります。
ここから、成功のポイントとなる要素を詳しく見ていきましょう。
【リスキリングを成功させるためのポイント】
・経営層が本気で取り組む
・目標が具体的である
・学びやすい環境が整っている
・部署を超えた協力がある
経営層が本気で取り組む
経営層がどれだけ本気かで、リスキリングの成否が決まります。
トップが明確なビジョンを示し、自らも学び続ける姿勢を見せれば、組織全体にリスキリングの大切さが染み渡ります。
会社の方針が伝わる
経営層は全社集会やイントラネットを使って定期的に情報を発信し、なぜリスキリングが必要なのか、何を目指すのかをはっきり伝えます。
また、各部門での説明会も開き、具体的なキャリアパスを示すことで、社員の理解と参加意欲を高められます。
トップが手本を示す
経営層自身が新しい技術やスキルを学び、その過程や成果を社内で共有します。
部門長クラスの管理職も率先して新しいスキルを身につけ、実務で使う姿を見せることで、組織全体の学ぶ意欲を引き上げられます。
目標が具体的である
2025年までにデジタル人材を今の1.5倍に増やすなど、数字で表せる目標を掲げることで、計画的に人材を育てられます。
目標をはっきりさせることで、組織全体が同じ認識を持ち、効果的な取り組みを進められます。
必要な能力が明確になる
各職種や役割に応じて必要なスキルをレベル別に定義し、「基礎」「応用」「実践」の3段階でスキルレベルを設定します。
| レベル | 内容 | 習得目標 |
|---|---|---|
| 基礎 | 基本的な知識と操作スキル | 本知識の理解、ツールの基本操作 |
| 応用 | 実務での活用スキル | 実務課題への適用、部門内での活用 |
| 実践 | 高度な活用と応用 | プロジェクト推進、他メンバーへの指導 |
業界で広く使われているスキル指標や資格制度と連動させれば、客観的な評価基準を作れます。
段階的な計画がある
「3ヶ月後にここまで」「半年後にここまで」と具体的な期間で区切った目標設定が効果的です。
一足飛びに高度なスキルを身につけるのは難しいので、着実に積み上げていく計画が必要になります。
ただし、個人の学習ペースや繁忙期などの業務状況に応じて計画を柔軟に調整できる仕組みも大切です。
学びやすい環境が整っている
リスキリングを推進する上で、「学びやすい環境」の整備は重要です。
今では、社内にデジタル学習プラットフォームを構築して、いつでもどこでも学べる環境を整備している企業もあります。
中には業務時間の一定割合を学習に充てられる制度を導入するなど、実践的なスキル習得を積極的に支援する会社も出てきました。「学び続ける組織」への転換のためには、時間と場所の確保、そして学習を評価する文化をつくることが欠かせません。
学習時間が確保できる
「忙しくて学習の時間が取れない」という課題に対応するため、週に1日は学習に専念できるような日を導入するのもよいでしょう。
業務時間内に学習の時間を確保することで、「仕事と学びの両立」という難題を解決することができます。
特に繁忙期における学習時間の確保方法や、部門間での業務調整の仕組みなど、実務的な部分までしっかり設計することが成功のポイントとなります。
オンラインで学べる
時間や場所の制約なく学習できるeラーニングシステムを導入し、スマートフォンやタブレットからもアクセス可能な学習環境を整備しましょう。
・進捗管理機能
・学習履歴の記録
・オンラインでの質問、相談機能
こういった学習をサポートする機能を備えることで、効果的な自己学習が可能になります。
部署を超えた協力がある
部署横断的なプロジェクトチームを作ることで、異なる専門性を持つメンバー同士が学び合うことができます。
これにより、新しい視点や発想が生まれ、イノベーションの創出にもつながります。
情報共有の仕組みがある
社内SNSやナレッジ管理システムを活用し、学習成果や実践事例を組織全体で共有できる仕組みを構築しましょう。
また、定期的な成果発表会や事例共有会を開催し、対面でのコミュニケーションも促すことも効果的です。
相互学習の機会がある
部署横断的な勉強会やワークショップを定期的に開催し、メンター制度やバディ制度を導入することで、経験者が初学者をサポートする体制を整えることができます。
例えば、プロジェクト型の学習機会を設けることで、実践的なスキル習得と部署間の協力関係強化を同時に行うことも可能でしょう。
リスキリングで注意すべき課題と対策
リスキリングを進めようとすると、思いのほか難しい壁にぶつかることがあります。
実は、うまくいかない理由には共通点があるのです。ここでは現場で本当に効果を出すための具体的な対策を解説していきます。
【リスキリングで注意すべき課題と対策】
・目的と効果が不明確になりやすい
・社員の自主性に任せすぎてしまう
・学習内容が実務と乖離している
・世代間でのデジタルスキル格差が広がる
・学習の継続性が保てない
目的と効果が不明確になりやすい
帝国データバンクの調査を見ると、リスキリングに取り組む企業はわずか8.9%にとどまっているのです。なぜこんなに少ないのでしょうか。
その大きな理由は、「なんとなく必要だから」と始めてしまい、本当の目的や期待する効果が曖昧なまま進めてしまうケースが多いためです。
リスキリングは企業の成長戦略と深く結びついていないと効果が出ません。特に大事なのは、「なぜ今、このスキルが必要なのか」を経営課題と明確に紐づけることです。
事業戦略と連動した目標を立てる
「3年後にこんな事業を展開したい」「このデジタルサービスを社内で開発できるようになりたい」など、具体的なビジョンから逆算して必要なスキルを洗い出すのが効果的です。
例えば、「デジタルマーケティングスキルの習得により顧客接点を30%増加させる」という数値目標を定めまた場合、このように具体的な数字があると、成果が見えやすくなります。
必要なスキルを洗い出して共有する
「今の業務に必要なスキル」と「将来必要になるスキル」を整理して、スキルマップを作ることをお勧めします。
例えば、製造業の現場では、社員が「自分はプログラミングなんて無理」と思い込んでいても、スキルマップで「基礎→応用→実践」と段階を示すことで、「まずは基礎からなら挑戦できそう」という前向きな反応が増えるでしょう。
定期的なスキル評価も大切です。半年に一度など、習得状況を可視化することで、「ここまでできるようになった」という達成感も得られます。
社員の自主性に任せすぎてしまう
「やる気のある人だけ学んでください」
これは失敗パターンの典型です。
自主性だけに頼ると、積極的な一部の社員だけが学び、組織全体のスキル底上げにはつながりません。
特に業務が忙しい時期には、自己学習の優先度はどうしても下がってしまいます。個人の意欲だけでなく、組織としてのサポート体制が不可欠です。
毎月の進捗状況を確認する
「学びっぱなし」にしないことが重要です。
例えば、月に一度の面談で学習の進捗状況を確認し、つまずいているポイントをその場で解決する取り組みを行うことが効果的です。
専門チームがサポートする体制を作る
「困ったときに相談できる人がいる」これだけで学習の継続率は大きく変わります。
リスキリング推進の専門チームを設置し、学習プログラムの選定から個別相談、成果の評価まで一貫してサポートする体制が効果的です。
学習内容が実務と乖離している
「研修で学んだけど、実際の業務で使えない…」
これはリスキリングの大きな落とし穴です。
机上の理論だけでは、実践的なスキルは身につきません。
特にデジタルスキルは、実際に手を動かしてみることが何より大切です。
実践的なケーススタディを取り入れる
実際の業務データや課題をベースにしたケーススタディが効果的です。
例えば、自社の顧客データを匿名化して分析演習に使ったり、現在進行中のプロジェクトを題材にしたワークショップを行ったり。具体的な事例を通じて学ぶことで、「どう現場で活かせるか」がイメージしやすくなります。
業務の中で実践する時間を作る
学んだことを試せる場を意図的に作ることが重要です。
例えば、「金曜日の午後は新しいスキルを使う時間」と定め、業務の一部で新しいツールやメソッドを試す取り組みを行うことが考えられます。
最初は小さなプロジェクトから始め、段階的に実践機会を増やしていくのがポイントです。
世代間でのデジタルスキル格差が広がる
これは多くの企業で見られる課題です。デジタルネイティブ世代の若手とベテラン社員では、そもそものデジタルへの親和性に差があります。
経営者の多くがデジタル化推進を考える一方で、ミドル・ベテラン社員のデジタルスキル習得意識が低いことも課題になっています。
この格差を放置すると、「若手だけに任せきり」になったり、逆に若手社員の不満から早期離職につながったりする恐れもあります。
年齢層に応じた学習内容を用意する
例えば、地方企業ではベテラン社員向けに「スマホの便利な使い方」から始めるなど、身近なデジタル機器の活用からスタートすることが効果的です。
いきなり難しいプログラミングから始めるのではなく、日常で使えるデジタルスキルから入ることで、抵抗感なく学べる環境を作れるでしょう。
段階的に習得できる仕組みを整える
誰もが自分のペースで学べる環境づくりが大切です。特に、これまでデジタルスキルが必要なかった部署の方々には、より丁寧なサポートが必要になります。
基礎から応用まで、自分の習熟度に合わせて進められる仕組みや、分からないところを何度でも質問できる雰囲気づくりも重要です。
学習の継続性が保てない
こちらも同様に帝国データバンクの調査によると、リスキリングに取り組む企業の42%が「従業員のモチベーション維持が難しい」と回答しています。
特に日常業務との両立や、学習成果が実感できないことが継続を妨げる大きな要因になっています。
業務時間内に学習時間を確保する
「業務が忙しくて学習する時間がない」これは特に多い声です。業務時間内に学習時間を確保することが、継続できるポイントとなっています。
週に半日でも良いので、「この時間は学習に充てる」と決めておくことが大切です。
特に繁忙期でも時間が確保できるよう、部署間で協力する体制も必要になるでしょう。
毎月の振り返りの場を設定する
定期的な振り返りの機会があると、モチベーション維持に効果的です。
「学んだことで何ができるようになったか」「どんな課題に直面しているか」を共有する場を設けることで、一人で抱え込まずに済みます。
特に実務での活用事例や成功体験の共有は、他の社員にとっても良い刺激になるでしょう。
リスキリングのまとめ
ここまで見てきたように、リスキリングは会社にも社員にも良い影響が多いのです。
デジタル化の波に乗り遅れないか心配している企業は多いですが、今いる従業員全員の新しい可能性を引き出すことで、その悩みを解決できるのです。
考えてみると、中途採用は本当にお金がかかります。しかし、社内の人材を育てれば、その分のコストを大幅に削減できます。
さらに、長い目で見れば、会社が本当に必要とする人材を確実に育てられるという安心感もあります。
社員の立場からすると、「自分の市場価値が上がる」というのは大きな魅力のひとつになるのではないでしょうか。今の時代、一つの会社に一生勤めるという時代ではなくなってきていることもあり、どのようなスキルを持っているかが将来を左右します。
もちろん、課題もあります。「なんのためにやるの?」がはっきりしなかったり、若手とベテランでデジタルへの親しみやすさに差があったり、日々の業務に追われて学び続けるのが難しかったり…。
しかし、こういった課題も、しっかり計画を立てて、適切なサポートがあれば乗り越えられるはずです。

「CBASE 360°」は、株式会社シーベースが提供するHRクラウドシステムです。経営を導く戦略人事を目指す人事向けのお役立ち情報をコラムでご紹介します。







![[記事内]サイド上部バナー(5分でわかる)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/cbase360_banner576x480.png)
![[記事内]サイドバナー(マンガ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_manga.png)
![[記事内]サイドバナー(導入事例)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_case.png)
![[記事内]サイドバナー(FAQ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_FAQ.png)
![[記事横]サイドバナー(よくある不安)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/e41db64088c81dc2b01f6f18514229af.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:管理職育成)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f103c8bbce2fadd324a0c8d3d3ac120a.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:ハラスメント)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/adf40fb044dc7223f6a77290b1efd5cd.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:評価制度の見直し)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/321f1a42ffe5917a57116bcaebe22a2a-1.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:離職防止)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/9fcf1dc0ac4bd1baccfa620cbd153ed2-1.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:エンゲージメント)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/c9e6bc632d13159f8823cbe753512d11.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:理念浸透)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f7d4e2070cebbb09bf70d724631a844a.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:次世代リーダー)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/2da0e900b4589c6d2ee5737a841d5a9e.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:ダイバーシティ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f6330b27ed0e940f37eb9f291bb951a2.png)

