36協定(サブロク協定)とは?残業時間の上限と注意点を徹底解説
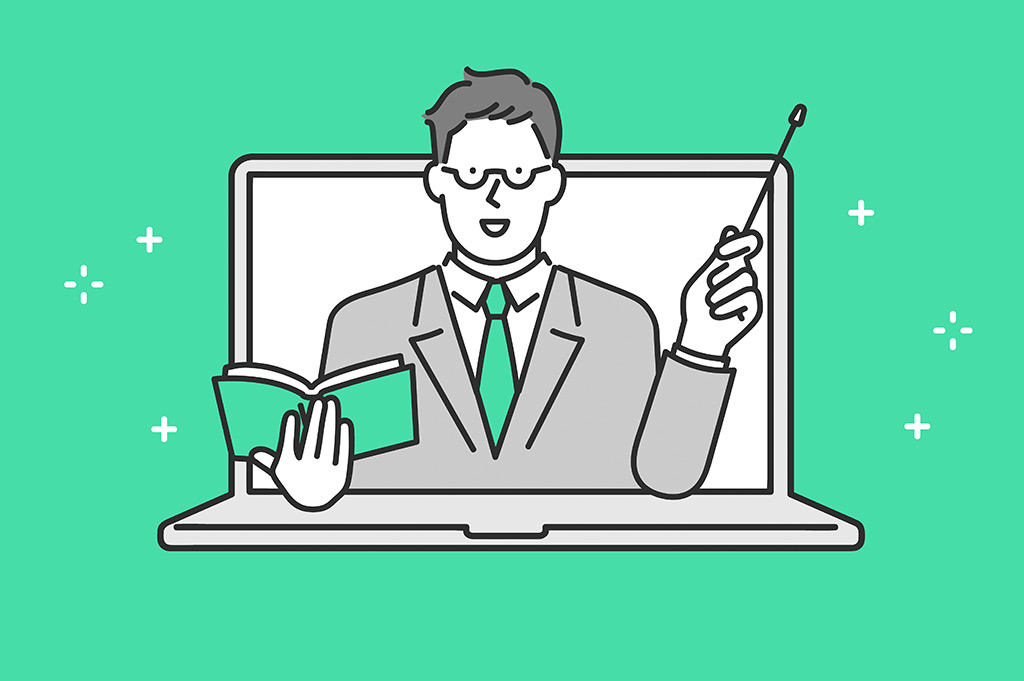
企業の人事部門では、36協定の実務における手続きの進め方や、法改正後の運用について不安を抱えるケースが少なくありません。
こうした実務上の課題は、企業経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。実際、36協定の手続きや運用を誤ると、企業は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった厳しい罰則を受ける可能性があります。
しかし、36協定の基本的な知識と実務のポイントを押さえておけば、こうした問題は防ぐことができます。適切な運用ができれば、従業員の健康管理と企業の生産性向上の両立にもつながります。
そこでこの記事では、人事担当者が知っておくべき36協定の基礎知識から実務のポイント、さらには産業別の注意点まで、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
目次
36協定とは
36協定(サブロク協定)は、労働基準法第36条に基づいて、労働者の代表と使用者(社長や事業所長など)の間で結ばれる協定です。
この協定を結ぶことで、法定労働時間を超える残業や休日出勤が可能になります。
ただし、協定を締結した後は、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定には「一般条項」と「特別条項」があり、一般条項では月45時間・年360時間を上限とする残業が認められます。
一方、特別条項を設ければ繁忙期など特別な場合に限り、この上限を超える残業も可能です。ただし、その場合でも年720時間以内、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内といった厳しい制限が設けられています。

労働基準法第36条に基づいて従業員の権利を守る
労働基準法第36条は、従業員の権利を守りながら、企業が柔軟に業務を進められるようにする大切なルールです。
この法律に基づく「36協定」では、労働者の代表と使用者が話し合い、時間外労働や休日労働の条件を決めます。
また、36協定の目的は、法定労働時間を超える労働を可能にする一方で、従業員の権利をしっかりと守ることです。企業が時間外や休日労働を命じる場合には、割増賃金の支払いが義務付けられていますし、その内容は厚生労働大臣が定めた指針に従う必要があります。
残業時間の上限を定めて過重労働を防止する
過重労働を防ぐために労働基準法が改正され、残業時間の上限が厳しく設定されました。
企業は従業員の健康を守るために、衛生委員会などを活用して過重労働対策の体制を整えることや、時間外や休日労働の削減に取り組む必要があります。
さらに、労働時間を適切に管理し、月100時間を超える時間外労働を行った従業員には産業医との面談を義務付けることが求められています。
これらの対策を実施することで、従業員の健康を守りながら生産性の向上も目指せます。過重労働による健康障害を防ぐためには、有給休暇の取得促進も欠かせないポイントです。
2019年の法改正で規制が強化されている
2019年4月の労働基準法改正では、時間外労働の上限が大きく見直されました。
この改正により、月45時間・年360時間という上限が罰則付きで導入され、特別条項を設けた場合でも年720時間以内に収める必要があるという厳しい規制が設けられました。また、中小企業には1年間の猶予期間が与えられ、2020年4月から適用されています。
さらに、年次有給休暇の取得促進や勤務間インターバル制度など、健康と生産性向上を両立させるための施策も盛り込まれています。
36協定における残業時間の上限規制
36協定における残業時間の上限規制は、2019年4月の労働基準法改正により厳格化されました。
これらのルールについて、下記で詳しく解説します。
【36協定における残業時間の上限規制】
・通常の残業は月45時間・年360時間まで
・特別条項があれば年720時間まで延長できる
・時間外、休日労働の合計を月100時間未満に抑える
・複数月平均で月80時間以内に収める
・休日労働も含めた総労働時間を厳格に制限する
通常の残業は月45時間・年360時間まで
36協定の一般条項では、通常の残業時間の上限が月45時間・年360時間と決められています。
企業はこの基準を守りながら業務を進める必要があり、そのためにはいくつか注意すべきポイントがあります。
例えば、36協定を結んでいない場合、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業は認められません。また、上限を超えた残業を行うと罰則の対象になる可能性もあります。
特別条項があれば年720時間まで延長できる
36協定の特別条項を設けることで、通常の上限である年360時間を超えて、最大で年720時間まで時間外労働が可能になります。
ただし、この特別条項を使うには、下記のような条件を守らなければなりません。
・月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満に抑える
・2〜6ヶ月の平均では80時間以内にする
・月45時間を超える時間外労働は年間6回まで
さらに、この特別条項は「臨時的な特別の事情」がある場合に限られ、その理由や対象となる業務、労働者数を明確にする必要があります。
時間外、休日労働の合計を月100時間未満に抑える
36協定の中で特に重要な規制の一つは、時間外労働と休日労働を合わせた時間を月100時間未満に抑えることです。
これは特別条項があるかどうかに関係なく適用されます。
また、月80時間を超える時間外労働を行った場合には、産業医による面接指導が義務付けられるなど、安全対策も強化されています。
複数月平均で月80時間以内に収める
36協定における時間外労働の規制では、2〜6か月の平均で月80時間以内に抑えることが求められています。
このルールは、単月で100時間未満という上限とセットで適用されており、長期間にわたる過重労働を防ぐための重要な仕組みです。
具体的には、任意の2〜6ヶ月間の平均時間外労働が80時間を超えてはいけません。例えば、3月に70時間、4月に95時間の残業があった場合、2ヶ月平均は82.5時間となり、この規制に違反してしまいます。
休日労働も含めた総労働時間を厳格に制限する
36協定での時間外労働の上限規制は、休日労働を含めた総労働時間を厳しく制限しています。
たとえ特別条項を設けた場合でも、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、さらに2〜6か月平均で80時間以内に抑える必要があります。
企業がこれらの規制を守るためには、総労働時間の正確な把握や管理が求められます。また、時間外労働の上限である年720時間以内を守ることや、長時間労働者への医師による面接指導など、健康確保のための措置も必要です。
36協定の締結方法と具体的な手続き
36協定の締結には、労働者の代表と使用者が合意形成を行い、適切な手続きを踏む必要があります。
下記では、それぞれの手続きについて詳しく解説します。
【36協定の締結方法と具体的な手続き】
・従業員の過半数代表と使用者が合意して締結する
・労使で合意した内容を所定の様式に記入する
・締結から2週間以内に労働基準監督署へ提出する
・有効期限は最長1年間で期限前に更新する
従業員の過半数代表と使用者が合意して締結する
36協定の締結には、従業員の過半数代表と使用者の合意が必要です。
もし労働者の過半数で組織する労働組合が存在しない場合は、民主的な手続きで選ばれた労働者の過半数代表者が協定を結びます。
この代表者は管理職ではない一般従業員から選出される必要があり、使用者が指名したり、社員親睦会の幹事をそのまま当てはめたりすることは認められていません。
選ばれた代表者は、使用者と協議を重ねて36協定の内容を決めていきます。
労使で合意した内容を所定の様式に記入する
36協定の締結後、労使で合意した内容を「36協定届」という所定の様式に記入する必要があります。
この様式は厚生労働省が定めたもので、電子申請の場合はオンラインフォームに必要事項を入力します。
記入項目としては、事業場の名称・所在地、時間外労働を行う理由や業務の種類、労働者数、延長可能な時間数などが挙げられます。
また、「36協定届」が労使間の合意を証明する「協定書」を兼ねる場合には、労使双方の署名や押印が必要です。特別条項を設ける際には、その理由や適用範囲も明確に記載しなければなりません。
36協定の起算日の前日までに労働基準監督署へ提出する
36協定届の提出期限は、協定の起算日の前日までです。
例えば、4月1日から協定を適用する場合、3月31日までに提出する必要があります。提出が1日でも遅れると、その期間の時間外労働や休日労働はすべて労働基準法違反となるため、注意が必要です。
提出方法には、労働基準監督署への直接持参、郵送、電子申請の3つがあります。
電子申請の場合、e-Govを通じて行うことができます。提出後は、労働基準監督署から受付印が押された控えが返却されるので、大切に保管しましょう。
有効期限は1年間で期限前に更新する
36協定の有効期間は、一般的に1年間とされています。
労働基準監督署の指導方針でも最長1年が望ましいとされており、多くの企業がこの期間を採用していますが、最長3年まで設定可能です。
また、有効期限が切れる前には更新手続きが必要です。例えば、4月1日から1年間の有効期間であれば、更新は3月末までに行う必要があります。
36協定における労働者代表の選出方法
36協定における労働者代表の選出は、民主的で公正な方法が求められます。
例えば、無記名投票や挙手、持ち回り決議などの手法が一般的ですが、特に大切なのは過半数の労働者から支持を得ることです。
それでは、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
【36協定における労働者代表の選出方法】
・投票や挙手などの民主的な方法で代表者を選ぶ
・管理監督者は労働者代表になることができない
・選出の記録を保管して適正な手続きを証明する
・全従業員に選出過程を公開して透明性を確保する
投票や挙手などの民主的な方法で代表者を選ぶ
36協定における労働者代表の選出は、全員の意見をしっかり反映できるよう、民主的で透明性の高い方法で行うことが大切です。
たとえば、無記名投票や挙手といった方法がよく使われています。無記名投票は特に公平で、従業員が多い会社に向いています。
一方、挙手は候補者を募った後に直接支持を表明するシンプルな方法です。
また、持ち回り決議という形で各部署の代表者が話し合う方法もあります。
選出の際には、まず目的をはっきりさせて全員に知らせることが重要です。そして、結果をすぐに公表して記録を残すことで、信頼感や透明性を保つことができます。
管理監督者は労働者代表になることができない
36協定の労働者代表の選出では、管理監督者は労働者代表になることができません。
これは労働基準法施行規則第6条の2により明確に規定されています。管理監督者は経営者と同じような立場とみなされるため、一般の従業員の利益をしっかり守るのが難しいと考えられているからです。
ただし、もし事業場に管理監督者しかいない場合には、例外として管理監督者でも民主的な方法で選ばれれば、賃金控除に関する労使協定などの締結者になることが認められています。
選出の記録を保管して適正な手続きを証明する
36協定の労働者代表を選ぶとき、その過程が正しく行われたことが分かるように、選出の記録をしっかりと保管することが大事です。
選出方法や結果を文書にまとめて保存しておけば、労働基準監督署の調査や従業員からの質問にも対応しやすくなります。
記録には、選出の日時や場所、方法(投票や挙手など)、候補者と得票数、選ばれた代表者の名前、そして選出に参加した従業員の人数を含めると良いでしょう。
これらは電子データとして保存することも可能で、オンラインツールを使えば、より正確で客観的な記録を残せます。
全従業員に選出過程を公開して透明性を確保する
36協定における労働者代表の選出過程を透明にすることは、従業員の信頼を得るためにとても大切です。
選出の流れを全員に公開することで、代表者が正当な方法で選ばれたことが分かるため、36協定の信頼性も高まります。
透明性を確保するためには、選出の目的や方法を事前にメールや掲示板で知らせることが重要です。また、立候補や推薦の過程を公開し、投票結果や得票数なども公表します。
36協定の産業別・業種別の注意点
36協定の適用は、産業や業種によって違いがあります。
各業種の特性に合わせた規制を正確に把握し、適切に運用することが重要です。労働者の健康管理に十分配慮し、長時間労働による健康障害を防止する措置を取る必要があります。
下記では、産業別・業種別の注意点や違いについて詳しく解説していきます。
【36協定の産業別・業種別の注意点】
・2024年4月から建設業にも上限規制が適用された
・自動車運転業務には異なる上限規制を適用する
・新技術開発業務は適用除外として扱う
2024年4月から建設業にも上限規制が適用された
2024年4月から、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。
他の業種と同じように、建設業でも時間外労働に厳しい制限が設けられています。
具体的には下記の通りです。
・年間の時間外労働は720時間以内
・月あたり100時間未満(休日労働を含む)
・複数月の平均で80時間以内(休日労働を含む)
この規制によって、建設業界では長時間労働を減らし、働き方改革を進めることが求められています。
この課題は「建設業の2024年問題」として注目されており、従業員の健康を守りながら生産性を高める取り組みが必要とされています。
自動車運転業務には異なる上限規制を適用する
自動車運転業務では、2024年4月から一般労働者とは異なる時間外労働の上限規制が始まりました。
この規制は、下記の通りです。
・年間の時間外労働の上限が960時間以内
・1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
・複数月平均で80時間以内
この新しいルールを通じて、運転業務の特性に配慮しながらも長時間労働を減らす必要があります。
新技術開発業務は適用除外として扱う
新技術や新商品の研究開発業務は、36協定で定められた時間外労働の上限規制が適用されない特例があります。
この特例は、研究開発の仕事が特定の時期に集中しやすい性質を考慮して作られたものです。
ただし、適用除外だからといって、労働者の健康を無視してはいけません。1週間で40時間を超える労働が月100時間以上になると、医師による面接指導を促すことが義務付けられており、違反した場合には罰則もあります。
36協定違反による企業リスク
36協定違反は、企業にとって大きなリスクになります。
これらのリスクについて、下記で詳しく解説していきます。
【36協定違反による企業リスクと対応策】
・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる
・労働者から割増賃金の請求を受けることがある
・企業の社会的信用が大きく低下する
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる
36協定違反によって、法律的に大きな問題を引き起こす可能性があります。
たとえば、労働基準法第119条第1項によれば、違反した使用者には6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金が科されることがあります。
具体的には、下記のような状況が考えられます。
・36協定を結ばずに時間外労働や休日労働をさせる
・36協定で決められた時間を超えて働かせる
また、罰則の対象は企業だけに限らず、労務管理を担当する責任者も含まれます。
労働者から割増賃金の請求を受けることがある
企業が36協定を守らずに法定労働時間を超える残業をさせると、従業員から割増賃金を請求される可能性があります。
割増賃金は、月60時間までは25%以上、60時間を超える場合は50%以上の割増率で支払わなければなりません。
また、下記のように、割増賃金の請求に対して企業が気をつけるべきポイントがあります。
・管理職からの請求の場合はその人が管理監督者に該当するか慎重に判断すること
・深夜労働(22時から5時)には管理職でも割増賃金が発生すること
・労働時間を正確に記録し管理すること
未払いがあると法律違反になるため、従業員の権利を尊重し、問題が起きた際にはすぐに対応することが大切です。
企業の社会的信用が大きく低下する
36協定違反が発覚すると、企業の信用が大きく揺らぎます。
ただの法律違反では済まず、評判や信頼性に深刻なダメージを与える「レピュテーションリスク」となります。
具体的に、下記のような影響を与える可能性があります。
・取引先や顧客からの信頼を失い取引関係が悪化する
・人材採用が難しくなることや、従業員が辞めてしまう
・投資家からの評価が下がることで株価が落ち、資金調達が難しくなる
また、メディアに取り上げられて批判されることも避けられません。
こうした信用の低下は、一度失うと簡単には取り戻せないため注意しましょう。
36協定違反で是正勧告を受けた場合はすぐに改善することが重要
36協定違反で是正勧告を受けたら、まずは早めに対応することが大切です。
是正勧告自体には法的な強制力はありませんが、無視すると立入検査や書類送検といった問題に発展する可能性があります。
最初に、どのような違反があったのかをしっかり確認して、社内で話し合いながら労務管理の問題点を洗い出し、改善策を考えましょう。
改善が終わったら、是正報告書を提出して再監督に備える必要があります。もし期日までに間に合わない場合は、担当の監督官に相談して対応方法を一緒に考えるのも手です。
こうした迅速で適切な対応をすることで、企業のイメージや取引先との関係への悪影響を最小限に抑えることができます。
36協定のよくある質問
36協定に関するよくある質問を下記にまとめました。
企業の人事担当者や労働者の方の疑問解消に、ぜひ役立ててください。
【36協定のよくある質問】
・36協定はすべての企業が締結する必要がありますか?
・36協定の締結時期はいつですか?
・36協定を結んでいない場合の残業は違法ですか?
・残業時間が超過した場合はどうすればいいですか?
36協定はすべての企業が締結する必要がありますか?
いいえ、すべての企業ではありません。
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて従業員に残業をさせる予定がある企業のみ、36協定の締結と届出が必要です。
36協定の締結時期はいつですか?
労働基準法では、法定労働時間を超える労働を禁止しているため、時間外労働や休日労働を行わせる前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります
36協定を結んでいない場合の残業は違法ですか?
36協定を結ばずに従業員に残業をさせるのは、労働基準法違反で違法となります。
法律では、1日8時間、1週間40時間を超える労働は原則禁止されており、それ以上働かせるには36協定が必要です。
残業時間が超過した場合はどうすればいいですか?
残業時間が36協定の上限を超えた場合、企業はすぐに対応する必要があります。
例えば、下記のような対応を検討しましょう。
・特別条項付きの36協定を締結して労働基準監督署に提出
・業務量を見直して残業時間を45時間以内に抑える
・勤怠管理を行う
また、長時間労働の原因を分析して業務効率化や人員配置の改善を図ることも重要です。
36協定のまとめ
36協定(サブロク協定)は、企業の労務管理における重要な取り決めであり、適切な運用を行う必要があります。
実務において特に意識すべき重要なポイントは、以下の3つです。
・労働者代表の選出を民主的な手続きで行い、選出過程の記録を残す
・時間外労働の上限規制を遵守し、従業員の健康管理に十分配慮する
・期限切れによる無効を防ぐため、更新時期を適切に管理する
36協定は単なる規制や制限ではありません。従業員の健康を守りながら、企業の生産性を高めていくために重要なルールです。
適切な運用を行うことで、働きやすい職場環境づくりを進めることができます。
運用に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することで、自社に合った適切な対応が可能です。

「CBASE 360°」は、株式会社シーベースが提供するHRクラウドシステムです。経営を導く戦略人事を目指す人事向けのお役立ち情報をコラムでご紹介します。







![[記事内]サイド上部バナー(5分でわかる)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/cbase360_banner576x480.png)
![[記事内]サイドバナー(マンガ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_manga.png)
![[記事内]サイドバナー(導入事例)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_case.png)
![[記事内]サイドバナー(FAQ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_FAQ.png)
![[記事横]サイドバナー(よくある不安)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/e41db64088c81dc2b01f6f18514229af.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:管理職育成)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f103c8bbce2fadd324a0c8d3d3ac120a.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:ハラスメント)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/adf40fb044dc7223f6a77290b1efd5cd.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:評価制度の見直し)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/321f1a42ffe5917a57116bcaebe22a2a-1.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:離職防止)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/9fcf1dc0ac4bd1baccfa620cbd153ed2-1.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:エンゲージメント)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/c9e6bc632d13159f8823cbe753512d11.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:理念浸透)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f7d4e2070cebbb09bf70d724631a844a.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:次世代リーダー)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/2da0e900b4589c6d2ee5737a841d5a9e.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:ダイバーシティ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f6330b27ed0e940f37eb9f291bb951a2.png)

