360度評価の評価項目を解説|管理職・一般職での違いと活用ポイント

⇒『マンガでわかる360度評価』『5分でわかるサービス紹介』『導入事例集』の資料3点セットを一括ダウンロード
360度評価を運用する際に重要なことが「評価項目」の設定です。
評価項目をどう設定するかによって、360度評価(多面評価)の効果に大きな影響が出ます。本記事では、評価項目の考え方と設定のポイントを徹底解説します。
特に、管理職と一般職で区別して項目を設定することが重要になるため、なぜ分ける必要があるのか、どのような視点で分けて設定すべきなのか、といったことを解説します。
管理職と一般職評価項目例のあとには、評価項目を適切に設定するための具体的なポイントもご紹介します。
360度評価の管理職向け評価項目
360度評価(多面評価)では、管理職は部下や同僚など多方面から評価を受けます。評価者の立場が異なるため、管理職に求められる資質や能力に対する視点も多様です。
そのため、管理職向けの評価項目では、マネジメントに関する能力を中心に評価するのが一般的です。下記の項目について詳しく解説します。
・リーダーシップ
・組織運営能力
・人材育成
・自己啓発
・経営理念理解
・判断力
なお、360度評価の評価項目は大きく 「スキル」「ヒューマンスキル」「考え方」 の3つの観点に整理することも可能です。ここで紹介する管理職の評価項目も、この3観点に沿って位置づけられるものです。
リーダーシップ
360度評価(多面評価)の管理職向け評価項目の一つが「リーダーシップ」です。
リーダーシップとは、目標達成に向けて部下やチームに影響を与え、動機づける能力を指します。
具体的には、組織のビジョンや方向性を部下と共有し、中長期的な目標を一緒に追えるかどうかが評価されます。
例えば、5年後・10年後を見据えたビジョンを描き、それをメンバーにわかりやすく伝えられるか、社会や顧客にどう貢献するかを意識して行動できているかがポイントです。部下の意見を聞き、建設的なフィードバックを行える姿勢も重要視されます。
組織運営能力
360度評価(多面評価)の管理職向け評価項目の「組織運営能力」は、部下やチームをまとめて円滑に業務を進められる力のことです。
具体的には、メンバー一人ひとりが最大限の力を発揮できる環境をつくれているかが評価されます。例えば、部下の得意分野や性格を理解し、それに合わせた業務割り振りができているかどうかです。
また、メンバー間のコミュニケーションを活発にし、互いに助け合える関係を構築できているかも大切です。そのために会議の開催や情報共有の仕組みづくりなどを行い、チームとして一丸となれる体制をつくれているかが問われます。
この組織づくり能力と組織運営能力は、管理職にとって非常に重要な評価項目です。部下やチームメンバーからの信頼が厚ければスムーズな業務運営ができるようになりますし、逆にこれらの能力が低ければ業務の停滞につながります。
人材育成
360度評価(多面評価)の管理職向け評価項目の「人材育成」では、部下や後輩の成長をサポートできているかが評価されます。
具体的には、部下に合わせた目標を設定し、挑戦の機会を与えられるかが重要です。例えば、得意分野を生かしたタスクを任せることでやりがいを感じさせられるか、達成に向けて適切な助言や教育機会を提供できるかがポイントになります。
また、日常業務での取り組みに対して適切にフィードバックを行い、改善点と強みを明確に伝えられるかどうかも評価対象です。
自己啓発
360度評価(多面評価)の管理職向け評価項目の「自己啓発」とは、管理職自身がスキルアップや知識習得に取り組む姿勢を指します。
研修や資格取得、専門書の学習、業界動向の把握などを通じて、自らの成長に努めているかどうかが評価されます。
管理職は部下を育成する立場にあるため、自身が学び続けることで組織全体の水準を高める役割も担っています。
経営理念理解
「経営理念の理解」は、管理職が自社の掲げる経営理念やビジョンを正しく理解し、部下に対して日常業務の中で理念の実現・浸透を図れているかを評価する項目です。
例えば、「安全最優先」を掲げている会社であれば、管理職は部下に対して、安全を軽視せずに業務に取り組むことの大切さをどのように伝えているかが評価されます。ミーティング等の場を使って、安全を意識した働き方を徹底しているかがポイントになります。
また、管理職自身が経営理念を正しく理解した上で業務が行えているかどうかも評価される重要なポイントです。理念の実現に向けて先頭に立っているかが問われます。
判断力
「判断力」とは、状況を的確に把握し、最適な方針を示せる能力です。管理職には時間的制約の中で、最善の結論を出す能力が求められます。
具体的には、事業環境の変化や予期せぬ出来事があった際、冷静に状況を分析し、ベストな対応策を考えられるかどうかが評価されます。例えば、競合他社の影響で売上が落ち込んだ場合、値引きで対抗するのか、商品力の強化で差別化を図るのか、といった判断が問われます。
また、部下からの提案に対しても、その良し悪しを判断し、採用するか断るか素早く意思決定できるかどうかがポイントです。柔軟な発想を持ちつつ、判断の正確さとスピードが求められます。

360度評価の一般職向け評価項目
管理職だけでなく一般職についても多面的な評価が行われます。一般職であっても日々の業務を通じて部下や後輩の模範にならなければいけない立場にあるため、適切な評価項目の設定が必要です。
一般職向けの評価項目として、下記について詳しく解説していきます。
・やり切る力(業務遂行能力)
・論理的思考能力
・創意工夫
・コミュニケーション能力
・主体性
やり切る力(業務遂行能力)
360度評価(多面評価)の一般職向け評価項目の「やり切る力(業務遂行能力)」とは、仕事を最後まで粘り強くやり遂げる力のことです。
具体的には、与えられた業務の目的を理解した上で、障害があってもあきらめずに最後まで実行できているかが評価されます。例えば、新商品の販促資料を作成するタスクがあった場合、見せ方や内容を何度も修正しながらでも最良の状態で仕上げられるかがポイントです。
また、自分の業務がチームや会社の業績にどう関わっているかを意識しつつ、積極的に働けているかどうかも評価されます。顧客満足度の向上や社会貢献といった自分を超えた視点で仕事の意義をとらえられているかが問われます。
この「やり切る力」は一般職にとって基本的な能力の一つです。評価を通じてスキルアップが可能です。
論理的思考能力
360度評価(多面評価)の一般職向け評価項目の「論理的思考能力」とは、物事の本質を理解し、効率の良い解決策を導き出す能力のことです。
具体的には、仕事上の課題が発生した際に、その原因を探り根本的な解決方法を考えられるかが評価されます。例えば、商談の失敗が続いている場合、自分の提案力不足だけでなく、商品自体の魅力度や市場動向など多面的に分析できているかがポイントです。
また、提案した解決策を実行に移す段取りを論理的に立てられるかどうかも評価されます。作業手順を明確化し、優先順位づけた上で計画的に進められるかが問われます。
一般職にも論理的思考力は欠かせません。自分一人の力だけで完結する仕事は少ないため、周囲と連携しながら課題の本質を見極め、業務を遂行する思考力が求めらます。
創意工夫
360度評価(多面評価)の一般職向け評価項目の「創意工夫」とは、業務を改善し効率化を行うための思考力と実行力のことです。
具体的には、これまでと違う発想で業務プロセスを変えられるかどうかといった柔軟性が評価されます。例えば、時間のかかる入力作業を自動化するアイデアを提案し、実際にシステム改修を実現できたかがポイントとなります。
また、新しい商品やサービスを生み出すために、既存の枠にとらわれない斬新な発想ができるかどうかも評価されます。他の事例を参考にしたり、利用者の視点を持つといった着眼点を増やすことが期待されます。
単に与えられた業務を処理するのではなく、創意工夫を凝らして生産性向上に貢献することが求められます。
コミュニケーション能力
360度評価(多面評価)の一般職向け評価項目の「コミュニケーション能力」は、他者とうまく関わりながら仕事を進める力のことです。
具体的には、同僚が困っていることに対して積極的に助けることができるかといった点が評価されます。例えば、新人社員の分からないことがあれば丁寧に教える、忙しそうな同僚の仕事を手伝うなどの行動があげられます。
また、自分と意見が異なる人であっても柔軟に受け入れ、一緒に課題解決に取り組むことができるかどうかもポイントになります。固定観念にとらわれずに、多様な視点を理解しようとする姿勢が重要です。
主体性
360度評価(多面評価)の一般職向け評価項目の「主体性」とは、自分から進んで考え行動する能力のことです。
具体的には、上司からの指示を待つのではなく、自分の判断で行動できるかが評価されます。例えば、業務改善のアイデアを主体的に提案できるか、突発的なトラブルが起きた時に自分で最善の行動がとれるかがポイントです。
また、自分の担当する業務の責任を他人や環境のせいにせず、自分事として捉えることができるかどうかも評価されます。与えられた仕事に対して「やり遂げる」という強い思いを持てているかが問われています。

📘 360度評価の実践・運用・設問設計に役立つ関連記事まとめ
360度評価で評価項目を決めて運用する時のポイント
360度評価(多面評価)の評価項目を設計する際は、評価者の負担や被評価者への配慮を考え、項目数や内容のバランスに注意する必要があります。
また、評価を人事評価に直結させるのか、人材育成や組織文化の醸成に活かすのかといった目的と運用計画を明確に共有することも欠かせません。
近年は、心理的安全性や多様性の尊重を評価に取り入れる企業も増えており、職場の信頼関係や健全な組織運営につなげる動きも見られます。
以下に、評価項目を決めて運用する際の具体的なポイントを解説します。
・管理職と一般職で項目を分ける
・評価項目の数は適切な量に抑える
・選択式と記述式の設問をバランスよく用意する
・評価基準を統一する
・日常的な業務態度や職務遂行能力を評価する
・導入目的や運用計画を明確にして従業員と共有する
管理職と一般職で項目を分ける
管理職と一般職で異なる項目を設けることがポイントの一つです。
管理職と一般職では求められる役割や解決すべき課題が異なるため、それに応じた評価の観点や項目が必要になります。
例えば、管理職にはリーダーシップや組織運営能力、部下の育成など、マネジメントに関する能力の評価が中心となります。
一方、一般職には業務処理能力や創意工夫、チームワークなど、仕事の遂行に関する評価項目を設定することが多いです。
このように立場や役割に応じた異なる項目を設定することで、個人の強みや弱みを適切に把握し、成長につなげるフィードバックを行うことができます。
評価項目の数は適切な量に抑える
360度評価(多面評価)の評価項目数が多いと、評価者の負担が大きくなりすぎます。例えば、1人当たりの回答に30分以上かかるようでは、評価者の本業に影響が出かねません。
また、項目数が多いと1つ1つの設問を深く考える余裕がなくなり、浅い回答になりがちです。その結果、360度評価の質が低下し、フィードバック効果が薄れてしまう恐れがあります。
具体的には、全体の設問数は30前後、1人当たりの回答時間は15分程度を目処に設定することをおすすめします。
選択式と記述式の設問をバランスよく用意する
選択式の設問では、点数やレーダーチャートなどのグラフで視覚的に評価傾向を把握しやすいというメリットがあります。
一方、記述式の設問では、点数だけでは分からない具体的な行動の気づきを得ることができます。例えば、「コミュニケーション力に課題がある」というだけではなく、どのような場面でどのように行動しているのかを文章で示してもらうことで、より行動変容に繋がる効果的なフィードバックとなります。
評価データの分析にも活用できる選択式と、気づきや行動変容を促すことができる記述式をバランスよく用意することが大切です。
評価基準を統一する
360度評価(多面評価)の評価基準がバラバラだと、同じような業務をこなしている人でも評価に差が出てしまいます。
例えば、ある評価者は裁量の幅を大きく取って評価する一方で、別の評価者は細かいところまでチェックして厳しい評価を行う、という具合です。
こうした基準の違いがあると、被評価者からすると評価結果に納得しにくくなります。「なぜこの評価なのか」と疑問を抱いてしまうでしょう。
だからこそ、事前に評価基準を明確化し、統一的な尺度で評価することを徹底する必要があります。点数のつけ方や判断の基準を共有しておくことで、360度評価の公正性と信頼性を高めることができます。
日常的な業務態度や職務遂行能力を評価する
評価項目を設定する際は、日常的な業務態度や職務遂行能力を評価しましょう。
例えば、与えられた業務を確実に処理できるスピード感や完成度を評価したり、業務上の課題に直面した際の判断力や解決力を評価したりします。
また、顧客対応の丁寧さや同僚とのコミュニケーションの良し悪しなど、性格的な要素も日々の業務遂行に深く関わるため、これらも評価の対象とします。
このように日常業務の中での様々な場面を評価できる項目を設定することで、360度評価(多面評価)ならではの多面的な気づきを被評価者に与えることができます。
導入目的や運用計画を明確にして従業員と共有する
事前に導入目的と運用計画を明確にし、従業員と共有しておきましょう。
例えば、360度評価(多面評価)の導入目的を人事評価に直結させるのか、人材育成に重きを置くのか区別し、社員に共有する必要があります。
また、評価結果のフィードバック方法や頻度、対象者の範囲といった運用計画についても事前に決め、周知しておくことが重要です。
導入目的と運用計画を明確化しないまま360度評価を始めると、社員から制度自体への不信感が高まる恐れがあります。
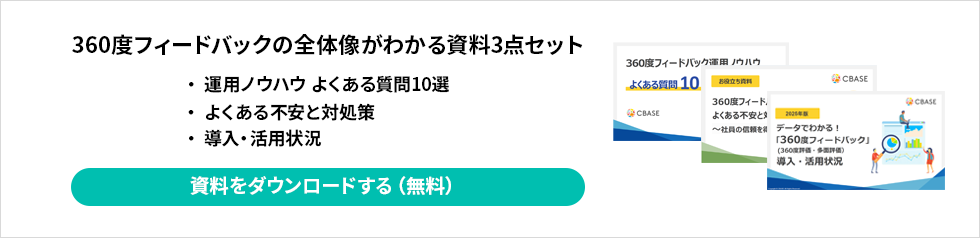
360度評価の評価項目まとめ
360度評価(多面評価)を効果的に運用するには、適切な評価項目の設定が欠かせません。管理職と一般職で区別した項目設定が基本となります。
管理職にはリーダーシップや組織運営能力などマネジメント面の項目が主体です。
一般職にはPDCAサイクルを回す実行力や創意工夫といった業務遂行能力を問う項目を中心に設定します。
また、評価者の回答しやすさと評価結果の活用の両立を考え、選択式と記述式の設問を組み合わせて作成します。評価基準と項目範囲を社内で統一することも合わせて重要になります。
項目設計を間違えてしまうと360度評価制度そのものの意味がなくなってしまうため、事前にしっかりと準備する必要があります。
FAQ(よくある質問)
Q1. 360度評価の評価項目はどのように設定すれば良いですか?
評価項目は「スキル」「ヒューマンスキル」「考え方」の3つの観点に整理するのが効果的です。例えば、スキルでは課題思考・課題遂行、ヒューマンスキルではコミュニケーション・組織貢献、考え方では責任感・誠実さ・前向きさといった姿勢を評価するのが一般的です。
Q2. 管理職と一般職で評価項目を分けるべきですか?
役割や責任の違いを反映させるために、分けて設計するのが望ましいです。管理職はリーダーシップ・人材育成・組織貢献などマネジメント力を中心に、一般職は業務遂行力・論理的思考・協働姿勢など個人スキルを重視するのが適しています。
Q3. 心理的安全性や多様性といったテーマも評価に含めるべきですか?
近年では「心理的安全性」「多様性の尊重」「ハラスメント防止」などを評価の観点に取り入れる企業も増えています。360度評価を単なる人事評価ではなく、組織文化を醸成し従業員の成長を支援する仕組みとして活用することが有効です。

「CBASE 360°」は、株式会社シーベースが提供するHRクラウドシステムです。経営を導く戦略人事を目指す人事向けのお役立ち情報をコラムでご紹介します。







![[記事内]サイド上部バナー(5分でわかる)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/cbase360_banner576x480.png)
![[記事内]サイドバナー(マンガ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_manga.png)
![[記事内]サイドバナー(導入事例)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_case.png)
![[記事内]サイドバナー(FAQ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_FAQ.png)
![[記事横]サイドバナー(よくある不安)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/e41db64088c81dc2b01f6f18514229af.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:管理職育成)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f103c8bbce2fadd324a0c8d3d3ac120a.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:ハラスメント)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/adf40fb044dc7223f6a77290b1efd5cd.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:評価制度の見直し)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/321f1a42ffe5917a57116bcaebe22a2a-1.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:離職防止)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/9fcf1dc0ac4bd1baccfa620cbd153ed2-1.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:エンゲージメント)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/c9e6bc632d13159f8823cbe753512d11.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:理念浸透)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f7d4e2070cebbb09bf70d724631a844a.png)
![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:次世代リーダー)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/2da0e900b4589c6d2ee5737a841d5a9e.png)
![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:ダイバーシティ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f6330b27ed0e940f37eb9f291bb951a2.png)


